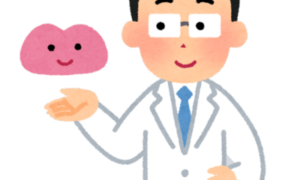 機械学習
機械学習 脳画像ビューワーの導入について
はじめに脳画像の研究を始めるにあたって、脳画像を実際に見る必要性があると思います。機械・深層学習をするにあたって、「ローデータ(生データ)」を確認することは重要であり、その場合はPythonで2次元でプロットすることもできますが、脳画像のビ...
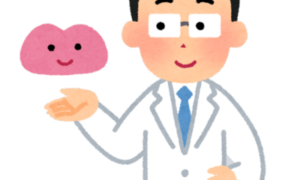 機械学習
機械学習 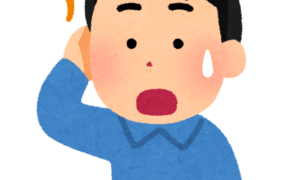 メンタルヘルス
メンタルヘルス  学会発表
学会発表  大学院
大学院  機械学習
機械学習  大学院
大学院  大学院
大学院 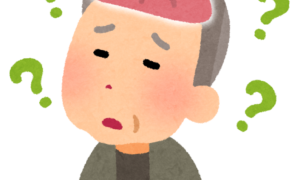 メンタルヘルス
メンタルヘルス  機械学習
機械学習  機械学習
機械学習